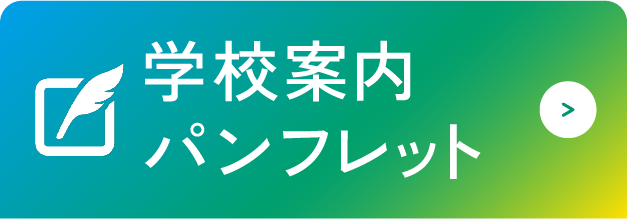スクールドッグが果たす学校の役割とは
本校では、今後スクールドッグの導入を予定しています。
本日教員研修で、SOCIAL ANIMAL BOND代表ならびに一般社団法人日本スクールドッグ協会代表理事である 青木潤一様に「スクールドッグ」の果たす役割やその教育的意義についてご講義頂きました。
単なる「癒し」や「かわいい存在」としての犬ではなく、子どもたちの心と成長に深く関わる存在として、スクールドッグが学校現場にもたらす影響について、多くの学びがありました。
スクールドッグは「セラピードッグ」と混同されがちですが、実際には明確に異なります。セラピードッグは医療現場で専門職が関与して行う「動物介在療法(AAT)」で用いられますが、スクールドッグは教育現場で活用される「動物介在活動(AAA)」の一環であり、医療的専門性を必要としないのが特徴です。つまり、犬が学校という日常空間に“存在する”こと自体が、子どもたちの心に働きかけるという教育的な活動なのです。
研修ではまず、「動物介在教育(AAE)」の意義が紹介されました。犬と関わることで、子どもたちは自己理解や感情コントロール、共感力、そして責任感や自発性といった、いわゆる「心の知能指数(EQ)」に関わる力を自然に育むことができます。これは、文部科学省の「生徒指導提要(2022年)」にも明記された「SEL(Social Emotional Learning)」の考え方と深くつながっています。
さらに、犬と関わることによって、子どもたちの心の中に「養護性(他者を気づかい、支えようとする気持ち)」が育ち、命を尊び、自ら探究するような行動へとつながっていくプロセスも紹介されました。犬との信頼関係を築く中で、自分自身と向き合い、他者とも安心して関係を結べるようになる――これは、今の学校現場で特に求められている教育のかたちではないでしょうか。
実際の学校現場での取り組みや実践の工夫についても共有されました。犬にも個性があるため、学校環境や子どもとの相性を見極めた上で、適切な接し方・飼育方法をとることが大切です。最初は犬の登場に子どもたちが過剰に反応してしまうこともありますが、徐々に落ち着き、自然な関係性が築かれていくとのことでした。また、犬アレルギーの児童がいる場合の対応としては、保護者への事前説明や、活動スペースの確保などが必要である点も強調されていました。
不登校の児童生徒が年々増加している一方で、学校における相談・支援の体制は十分ではありません。そんな今だからこそ、犬という「言葉を超えた存在」が、子どもたちの心を開くきっかけとなり、教師と子ども、また子ども同士の関係をも育む力を持っているのだと感じました。
特に印象的だったのは、「子どもが生まれたら犬を飼いなさい」という、イギリスの古くからのことわざの紹介です。その意味は、「犬を通じて、子どもは責任を学び、友情を知り、そして別れの悲しみを体験することで、人生において大切なことを自然に学んでいく」ということでした。
研修を通じて、スクールドッグは単なる「補助的存在」ではなく、学校教育の新たな柱としての可能性を秘めていると強く実感しました。子どもたちが安心し、自分らしく過ごせる空間づくりをめざすうえで、犬との共生教育は今後ますます重要になっていくのではないでしょうか。
※「スクールドッグ」は一般社団法人日本スクールドッグ協会が商標登録しています。