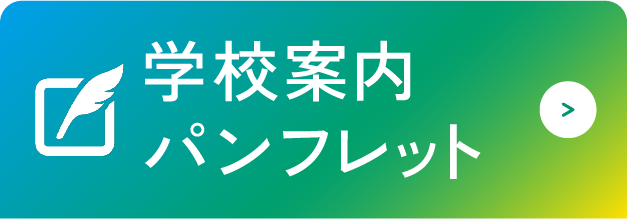校長日記612「特別支援教育研修会から」

健康支援センター主管で、特別支援教育研修会を開催しました。
島根県特別支援教育研修会に、本校もオンライン形式で参加し、多くの教員が研修を受けました。
講師は、信州大学医学部子どものこころの発達医学教室特任助教で小児科医の新美妙美先生です。発達障害、心身症、不登校支援の診療を、大学病院や一般病院の専門外来で専門的に行っておられる先生です。
先生はまず発達障害の特性について説明されたあと、次のような具体例を示してくださいました。ひとりや家族だけで悩まず相談できる場を作ること、大人になるまでに自分の特性に気付きヘルプを求められること、人を嫌いにならず信頼できる人がいること、学校だけでなく心地よい第3の居場所をつくること…。あっという間の2時間30分でした。終始力強く語りかけていただき、講義は楽しく集中して聴くことができました。ありがとうございました。
本校では、特別支援教育に全校で組織的に取り組んでいます。特別な教育的支援を必要とする生徒への指導をユニット担任に任せきりにするのではなく、全教職員が協力し、学校全体として組織的・計画的に進めることを明確に打ち出しています。
校内体制についても、校内支援委員会の設置、特別支援教育コーディネーターの指名、学校内外の人材活用、近隣の盲・聾・養護学校や関係機関との連携など、多方面から支援の実施・評価・改善に取り組めるよう推進しています。
しかしながら、学校はとても“狭い社会”だと感じたことはありませんか。もちろん、子どもたちが広い社会で生きていくための準備の場として、一定の「枠」があることは必要です。しかし時には、その枠が偏っていたり、社会の一般常識からかけ離れていたりすることもあります。
開星は、もちろん学力を伸ばすことを目指します。ただし勉強がどうしても苦手な子もいますので、それぞれに合った目標や成長の仕方を大切にしています。勉強が得意であることで広がる可能性も多くありますが、何よりも最優先というわけではありません。私は、一人ひとりに必ず輝く個性があると信じています。それが、創立100周年を終えてNext200に向けたテーマ「未来を開く星になる」に込めた思いです。だから、いろいろな成長の仕方があってよいのです。101年目の開星は、「みんな違ってみんないい」の精神で歩みます。
私たちの支援のあり方や理解の仕方が、非常に重要であることを、特別支援教育が正式に実施された2007年から感じ続けています。しかし常に100%正しい支援や理解ができていたわけではありません。このような研修を通して悩み続けること自体が、子どもたちの成長につながるのだと改めて感じました。
最後に、研修会を主管された健康支援センター長の大谷弘一郎主幹から振り返りがありました。この振り返りの時間がとても心地よく、本校の職員が「一人ひとりが主役の学校づくり」に向けて、目指す教師像「ともに学び、ともに成長する」を再確認できる大きな学びとなりました。